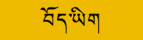誰と一緒にいる時でも
自分を誰よりも劣った者とみなし
他者を最もすぐれた者として
心の底から大切に慈しむことができますように
第一偈には、すべての有情を宝のように貴重な存在とみなす心を育む必要性が説かれていましたが、第二偈では、すべての有情を宝のように貴重な存在と認識した上で、彼らを劣った者と考えて憐れむのではなく、貴重な宝とみなす心を土台として大切に慈しむべきことが説かれています。ここで強調されているのはむしろ、すべての有情をよりすぐれた存在として心から敬い、尊敬する気持ちを土台として、有情を大切に慈しみ、貴重な宝と認識するべきだということです。ここで私は、仏教的な意味合いで慈悲の心をどのように理解するべきかをお話しておきたいと思います。一般的に言うと、仏教の伝統では、愛と慈悲の心は同じ事象が持つ二つの側面とみなされています。慈悲の心は、慈悲の対象となる有情たちが苦しみから自由になれるようにと心から願う気持ちであり、相手をやさしく思いやる愛情は、他者が幸せになれるようにと心から願う気持ちです。ですから仏教的な意味における愛と慈悲の心を、日常的に使われている愛と慈悲の意味に捉えてはいけません。たとえば、私たちは自分にとって愛しいと感じる人たちに対して親近感を持ちますし、彼らに対して慈悲の心で苦しみを分かち合いたいという感情を持ちます。そういう人たちに対しては強い愛情を持ちますが、この種の愛と慈悲は、「誰それは私の友人である」「私の配偶者である」「私の子供である」などというように、相手が自分に関係のある人だという認識に基づいていることが多いのです。そこでこの種の愛と慈悲はとても強い感情にもなりますが、この種の愛と慈悲の心に何が起こりうるかと言うと、自分に関係のある人だという認識が含まれているために、そこには執着の気持ちが入り込んできてしまいます。そして執着が混ざっていると、怒りや嫌悪が生じる可能性も出てきます。執着は怒りや嫌悪とともに存在しているからです。たとえば、誰かに対する慈悲の心に執着が入り込んでいる時は、些細な状況の変化によって、慈悲の心はいとも簡単に怒りという全く逆の感情に変わってしまいます。すると、相手の幸せを願うどころか、その人がひどい目に合うことを願ったりすることになりかねません。
心を訓練する修行において育むべき本物の愛と慈悲の心は、他者も自分と全く同じように幸せを望んでいて、苦しみを取り除きたいと願っており、他者も自分と全く同じように、この基本的な願いを達成する権利を本来的に持っているのだという認識に基づいていなければなりません。この基本的な事実を認識し、それに基づいて育む他者への共感こそ、普遍的な慈悲の心なのです。そこにはいかなる偏見も差別も含まれていません。この種の慈悲の心は、幸せと苦しみを体験することができるすべての有情を対象としています。つまり、本物の慈悲の心が持つべき特徴は、普遍的なものであり、一切の差別を含まないということなのです。そこで、仏教の伝統に従って慈悲の心を育むという心の訓練は、まず最初にすべての有情を同等にみなすという「平等心」を育むことから始めます。たとえば、誰それは今世における私の友人である、私の親戚であるなどという事実を思い浮かべてしまうかもしれませんが、仏教的に考えるならば、その同じ人が前世における最悪の敵であったかもしれないのです。これと同様に、あなたが敵だと思っている人に対しても、同じ論理を当てはめて考えることができます。つまり、その人は今生では大変ひどい人であり、敵となって現れているかもしれませんが、前世ではあなたの親友であったかも知れませんし、あなたの身近な関係者であったかもしれません。このように、他者と私たちの人間関係の本質は非常に移ろいやすいはかないものであるということや、すべての有情は友人にもなり、敵にもなりうる可能性を持った存在であることを考えて、すべての有情に対する平等心を育まなければなりません。
平等心を育む修行には、執着を離れるという実践も含まれてきますが、ここで執着を離れるという意味を正しく理解することが大切です。時々、執着を離れるという仏教の修行のことを聞くと、仏教はすべてのものに対して無関心な態度をとるべきだと説いているかのように誤解してしまう人もいるようですが、そうではありません。まず最初に、執着を離れるということは、相手が自分にとって遠い人か身近な人かという判断に基づいて、他者を差別する感情を取り除くものだと言ってよいでしょう。そうすることで、あなたはすべての有情を対象とする本物の慈悲の心を育むための土台を築くことができます。執着を離れるという実践についての仏教の教えは、この世界や有情との関わりを持たず、無関心な態度をとることを意味するのではありません。
次の行に移りますが、「自分を誰よりも劣った者とみなすことができますように」と述べられている言葉の意味を正しく理解することが大切だと思います。もちろんこの言葉は、自分を過小評価するような考えを持つべきだとか、すべての希望を失って、「私は最も劣った人間だ。私には何の能力もない。私は何もできず、何の力もない」と考えて落胆するべきだと言われているのではありません。そのようなことは、ここで言われている「劣った者」の意味ではないのです。「自分を誰よりも劣った者とみなす」とは、相対的な意味で理解しなければなりません。一般的に言えば、人間は動物よりすぐれています。私たち人間は正しいことと間違ったことを区別し、善悪の判断をする能力を持っていますし、将来のことを考える能力もあります。しかし別の観点から見れば、人間は動物たちより劣っているではないか、と言うこともできます。たとえば、動物たちは倫理観に基づいて何が正しく、何が間違っているかを判断する能力を持ち合わせていないかもしれませんし、自分の行動が将来どのような結果をもたらすかを見抜く能力もないかもしれません。しかし、動物の世界であっても、少なくともある種の秩序が存在しています。たとえばアフリカのサバンナ地方を見てみると、捕食動物たちは自分が空腹な時だけ必要に応じて他の動物を捕らえて餌食にしています。そして空腹でない時は、他の動物たちと平和的に共存しているのです。ところが私たち人間は、善悪の判断力を持っているにもかかわらず、ただ欲望に駆られて行動してしまうこともあります。まるでスポーツの感覚で、狩猟や魚釣りに行って動物を殺し、気ままな道楽に耽溺してしまうこともあるのです。ですからある意味では、人間は動物より劣っていることを証明できるという議論も成り立つことになります。つまり、私たちが他者よりも劣っているという見方は、そのような相対的な意味合いにおいて使われているのです。また、「より劣っている」という言葉を使っている一つの理由には、普段私たちが怒り、嫌悪、強い執着、欲望などの感情に屈服してしまう時、そういった感情を慎もうという自制心さえ持つことなくそれらの感情に支配されてしまっているということを強調するためなのです。私たちは、自分の行動が他の有情たちにどういう影響を与えるかなど全く気にせずにいることがよくありますが、他者は自分よりすぐれていて、敬意を表わすに値する存在であると考える心を意図的に育むことによって、自分自身を慎しむための要素として準備しておくことができます。すると、そのような悪い感情が起きてきても、他の有情たちに対する自分の行ないがもたらす影響を無視するようなことにはならず、それらの悪い感情が大きな威力を持つことにはなりません。ここで言われている他者を自分よりすぐれた者とみなす認識は、このような土台に基づいて提案されているのです。