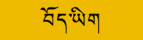私はすべての有情のために
如意宝珠にもまさる
最高の目的を達成しようという決意によって
常に有情を慈しむことができますように
この四行詩は、他のすべての有情たちを心から愛しいと感じる心を育むための教えです。この偈では、他の有情たちを如意宝珠のように貴重な宝とみなす態度を築くことがいかに大切であるかが強調されています。そこで、「何故私たちは、他の有情たちを貴重で価値あるものとみなさなければならないのか?」という疑問が生じてくるかもしれません。
ある意味で、他の有情たちは毎日の人間関係だけでなく、私たちが経験する喜び、幸せ、繁栄の主な源だと言えます。私たちが大切にし、得たいと望んでいる体験のすべては、他の生きものたちと協力し合ったり、交流したりすることで得られるからであり、それは実際に目で見て確かめることができる明らかな事実だからです。同様に、修行道の実践者であるという観点から考えても、あなたが得ている高度な理解と精神の旅における進歩は、他の生きものたちと協力し、交流することによってもたらされています。さらに、悟りという仏陀の結果の境地における本当に慈悲深い仏陀の行ないは、ただ有情たちとの関係において、何の努力も必要とせずごく自然になされています。何故ならば、有情たちは仏陀の慈悲を享受する者であり、覚者たちの行ないによってそのご利益を得る者だからです。ですから有情たちは、私たちに喜び、繁栄、幸せをもたらしてくれる本当の源だということを理解することができるでしょう。衣食住、友情、さらに名声などもそうですが、人生における基本的な喜びや快適な暮らしは、すべて他の有情たちに依存して得られるのです。私たちが快適だと思い、安全だと感じられるのは、他の人たちが私たちのことをどう思っているのか、そして私たちをどれだけ愛してくれているかによっています。つまり人間の愛情こそ、私たちの存在の土台だと言えるでしょう。私たちの人生は愛情なしに始まることはなく、私たちの生命維持に必要な滋養、適度な成長などをはじめ、すべては愛情に依存しています。平穏な心を築くためにも、他者に対する思いやりがあればあるほど、あなたが得る満足度はより深いものになるでしょう。あなたが相手に対する思いやりを持ったその瞬間から、その人はあなたにとって好ましい人として現われてきます。これはあなた自身の態度に依存しています。その逆に、もしあなたが相手を拒否すれば、その人は嫌な人として現われてくるでしょう。私にとって大変明らかなのは、自分のことだけを考えている時、あなたの心は狭いものになり、その視野の狭さのために、不愉快に感じる対象物が巨大に見えてきて、あなたは恐怖と不安と惨めさに打ち負かされているように感じてしまうのです。しかし、あなたが相手に対する思いやりを持てば、あなたの心はゆったりとした広いものになります。そして、広い視野に立って考えている時は、あなた自身が抱えている問題などたいしたことではないと感じられるのであり、これがとても大きな違いをもたらしてくれるのです。あなたが他者に対する思いやりを持っていれば、たとえあなたが問題を抱えていても、困難な状況に直面していても、内なる力を持った人に見えますし、そのような心の勇気があれば、自分が抱えている問題などたいしたことではないと感じられるので、それに惑わされることはありません。自分自身の問題を克服して他者に思いやりを持つ時、あなたは内なる力を得て、自信と勇気、平穏な心を持った人になることができます。これは、自分のものの考え方が大きな違いをもたらすということの明らかな例だと言えるでしょう。
シャーンティデーヴァ(寂天)の『入菩薩行論』には、自分が他者の苦しみを引き受けた時に体験する痛みと、自分自身の苦しみによって直接自分の身に生じる痛みとの間には、現象学的な違いがあると述べられています。前者の場合には、他者の苦しみを共に分かち合っていることから生じる不快感が存在します。しかしシャーンティデーヴァは、そこにはある程度の安定が存在すると指摘しており、それはあなたが意図的に喜んでその苦しみを受け入れているからなのです。つまり、自ら好んで他者の苦しみを分かち合うという選択をしているため、そこには内なる力と自信が存在しています。しかし後者の場合は、自分自身の痛みを味わっているだけなので、不本意にもいやいやながら苦しみを味わっているという気持ちがあり、自分自身をコントロールすることができず、自分は弱い人間であり、完全に打ちのめされていると感じてしまうのです。利他心と慈悲の心についての仏教の教えには、「自分の幸せを考えるのではなく、他者の幸せを大切にするべきである」という表現が使われています。他者の痛みや苦しみを共に分かち合うという修行についてこのように述べられているその意味を、正しく理解することが重要です。基本的には、もしあなたに自分自身を愛する力がなければ、他者に対する思いやりを築く土台がなくなってしまいます。自分自身を愛するということは、自分に恩義があるからではありません。私たちは皆ごく自然に幸せを望んでいて、苦しみを望んではいないという非常に根本的な人間の存在のありように基づいて、自分を愛する力を持ち、自分に対して親切であるべきなのです。いったん自分自身との関係においてこの土台を築くことができれば、それを他の有情たちにも広げていくことができます。ですから教えの中に、「自分の幸せを考えるのではなく、他者の幸せを大切にするべきである」という言葉を見つけた時は、理想とする慈悲の心に従って自分の心を訓練する、という文脈の中でこの言葉を理解する必要があります。もし、他者に対する私たちの行ないがその人にどんな影響を与えようとも気にしない、というような自己中心的なものの考え方をしているのでなければ、これは大変重要なことなのです。すでに述べましたが、私たちが喜びや幸せ、成功などを得ることができるのは、すべて他の有情たちのおかげであるということを認識することによって、彼らを宝のように尊い存在だとみなす態度を育むことができます。よく分析して考えてみるならば、私たちが経験する悲惨な出来事や苦しみの多くは、他者を犠牲にしてでも自分の幸せを得ようとする自己中心的な態度から生じた結果であり、その逆に、私たちが経験する喜びや幸せ、安全な暮らしなどの多くは、他の有情たちの幸せを願い、彼らを心から大切に慈しむ心から生じた結果であるということを知ることができるでしょう。
また、他の有情たちの幸せを願い、大切に慈しむ心を育むことに関連してもう一つの事実が存在します。他の有情たちのために働くことによって、自分の関心事や願いが叶うのであり、これらは利他行によって得られる副産物だということです。ツォンカパ大師も『菩提道次第広論』の中で、「修行者が他の有情たちの幸せのみを願う心を起こし、それを実践すればするほど、その人の修行の達成と理解度は、特別な努力を何も必要とせず、利他行の副産物として自然に達成される」と述べられています。私がよくお話しすることですが、仏教の修行を実践する慈悲深い菩薩たちは賢者の利己主義を実践し、私たちのような凡人がやっているのは愚か者の利己主義に過ぎない、ということを聞いたことのある人たちが皆さんの中にもいることでしょう。つまり、私たちは自分のことばかり考えていて、他者のことなどに関心を払わず、その結果として私たちは常に不幸であり、惨めな気持ちで人生を過ごしています。そこで、もっと賢くなるべき時が来ているのではないか、というのが私の確信です。しかしそれに対して、「私たちは本当に自分の態度を改めることができるのだろうか?」という疑問を持つ人が出てくるかもしれません。
そこで、私自身のささやかな体験に基づいてお答えするなら、「必ずできる!」とためらいなく言うことができます。私たちが「心」と呼んでいるものは、かなり特別な性質を持っています。時には非常に頑固で、心を変えることなどとてもできそうではありません。しかし、理由と根拠に基づいた確信を持ってたゆまず努力するならば、私たちの心はかなり正直で開かれたものに変えていけるのです。あなたが、心を入れ替えてよき変容をもたらさなければならないと心の底から感じているならば、あなたの心をより良く変えていくことは可能です。しかし、ただ単に変わりたいと願い、祈願するだけでは心によき変容をもたらすことはできません。ただし、正しい理由に基づく確信と、自分自身の体験に基づいた究極的な理由があれば、あなたの心をより良く変えていくことができるのです。そこで、その時期が大変重要な要素になりますが、機が熟せば、私たちの考えかたや態度は必ず変えることができます。ここで一つ指摘しておきたいのは、自分のことをとても現実的で実用本位な人間だと思っている人たちは、あまりに現実的過ぎて実用性に捉われ過ぎている面があるということです。そういう人たちは、「すべての有情の幸せを願ったり、彼らのことを心から慈しむなどという考え方を育むことは非現実的であり、あまりに理想的過ぎる。そんなことは全く不可能なことなのだから、有情たちの心によき変容をもたらし、ある種の精神的な規律を達成するためにいかなる努力も貢献もする必要はない」と考えてしまうかもしれません。すると、自分と直接交流のあるより親しい人たちだけを対象にして、もっと効果的な方法に取り組むべきではないのか、と考える人もおそらく出てくるでしょう。そういう人たちは、対象となる相手の範囲をあとで広げていけばよいと考えているのであり、有情の数には限りがないのだから、すべての有情のことを考えるなんて無茶だと思っているのです。彼らは、地球というこの惑星に住む人間たちに対しては、もしかすると何らかの関係があると感じているかもしれませんが、複数の惑星や限りない宇宙に住む無数の有情たちとは個人的な関係はないと考えているのです。そして、「限りない宇宙に存在するすべての有情を含めてそのような心を育むことに一体何の意味があるのか?」という疑問を持つかもしれません。これは、ある意味では考えるべき価値のある反論かもしれませんが、ここで重要な点は、そのような利他的な心情を起こすことによってもたらされる良き影響について理解することです。
つまり、この実践の大切な点は、痛みを感じ、幸せを経験する能力を持つすべての生きものたちを包めて、彼らが体験する苦しみと幸せを共感する努力をすることにあります。そして、命あるすべての生きものを、有情として、心を持つものとして、明確に認識することです。このような心情を持つことは非常に大きな力を発揮しますが、ある意味では、私たちがそのような心情を起こしたことで、それぞれの有情たちに何らかの良き効果があったかどうかを確認する必要はありません。たとえば、普遍的な本質である「無常」を例にとって考えて見ましょう。私たちが「諸行無常」(すべての物事や現象は無常であるということ)について思いを馳せる時、無常を確信するために、この宇宙に存在するすべての現象や物事について考える必要はありません。私たちの心はそのように働くのではなく、この点を理解することが重要です。
第一偈では、「私は常に有情を慈しむことができますように」と、直接的に「私」という主体者について述べられています。ここで、「私」とは何かということについて、仏教的な見解を簡単に説明しておくと役に立つでしょう。一般的には、あなたや私、それ以外の他の人たちが存在していることに対して異議を唱える人など誰もいません。つまり、痛みを体験する主体者となる人が存在するということに疑いを持つ人はいないのです。私たちは、「私はこのようなことを見た」「私はこのようなことを聞いた」などと言って、会話をする時は常に第一人称を示す名詞を使っています。ですから世俗のレベルでは、毎日の生活の中で私たちが体験している「自我」や「私」が存在していることに反論の余地はありません。しかし、そのような「自我」や「私」とはどういうものなのかを理解しようとすると、疑問が生じてきます。そこでこの疑問を解明するために「自我」について分析し、たとえば自分が若かった時のことを思い出してみるなどして、日常生活のレベルから少し拡張して考えてみるのです。そのようにして若い頃の自分を思い出してみると、若かった頃の自分のからだと「自我」の感覚との間には類似した一体感が生じます。あなたが若かった時、「自我」は確かに存在していましたし、あなたが年をとっても「自我」は存在しています。そして若かった時と年をとった時のどちらにも共通する「自我」も存在しています。人は誰でも自分が若かった時のことを思い出すことができますし、自分が年をとった時のことを考えることもできるのであり、その時の自分のからだの状態、「自我」の感覚、自分という意識には非常に近い一体感を認めることができるのです。多くの哲学者や、特に宗教思想家たちは、時間を越えて継続的に存在する個人の「自我」や「私」についての探求をしてきました。それはインドの伝統の中で特に重要視されています。非仏教徒たちのインド哲学学派では、「アートマン」の存在を主張しており、これは大まかに「自我」「魂」などと訳されています。そして、インド哲学以外の宗教では、生きものたちの「魂」の存在を主張しています。インド哲学が主張する「アートマン」には、個人が経験する現実とは全く無関係に独立して存在する主体者、という特別な意味があります。たとえばヒンドゥー教の伝統では生まれ変わりを信じており、これは多くの論議を巻き起こしてきました。私も、神秘的な修行のひとつに意識、あるいは「魂」が死んだばかりの人のからだに乗り移るという例があるのを見つけたことがあります。もし私たちが生まれ変わり、私たちの「魂」が他者のからだに乗り移って存在し続けるということがあるならば、個人が経験する現実とは無関係に独立して存在する主体者としての「魂」が存在すると想定しなければなりません。全体的に見れば、非仏教徒たちのインド哲学学派では、多かれ少なかれ、「自我」とはまさにこの種の独立した主体者、あるいは「アートマン」のことであるという結論に達しています。それはつまり、私たちのからだと心とは無関係な、それ自体で独立した存在のことです。一方で、全体的に見た仏教の伝統では、私たちのからだと心とは無関係な、それ自体で独立して存在している「自我」や「アートマン」、「魂」が存在するという考え方は否定されており、仏教の哲学学派では、「自我」や「私」はからだと心の構成要素の集まりとして理解されるべきであるという一致した見解を持っています。しかし、私たちが「自我」「私」と言う時、それが正確に何を意味しているのかという点に関しては、仏教哲学の思想家たちの間にも相違があるのです。多くの仏教哲学学派は、最終的な「自我」の考察において、「自我」とはその人の意識であるという立場を取っています。分析と考察を通して、私たちのからだがいかに他のものに依存した不確かな存在であるかを知り、時を越えて存在し続けるのは有情の意識であるということを私たちは示すことができるのです。
もちろんその他の仏教思想家たちには、「自我」は意識であるという考え方を否定する人たちがいます。ブッダパーリタ(仏護)やチャンドラキールティ(月称)などは、永遠に存在し続ける恒常的な「自我」を想定することを断固として否定しています。彼らはそのような理論に従うことは、根深い実体への捉われに屈してしまうことになると述べているのです。第一偈で「自我」の本質を分析することは、形而上学的な自我の探究なので、その分析が何かをもたらすことはありません。それは、ブッダパーリタやチャンドラキールティが論破している実体を持つ「自我」についての探求であり、私たちは日常的な言葉と経験に基づく理解をはるかに超えた領域の話をしようとしているのです。ですから、「自我」「人」「主体者」などは、私たちが「自我」の感覚をどのように体験しているかという脈絡の中で純粋に理解されなければならず、世間的なレベルにおける「自我」や「人」の理解を超えるべきではありません。私たちは、肉体的・精神的な存在として自分は存在しているのだという理解を高めていくべきであり、そうすることにより、「自我」や「人」はある意味で、からだと心に依存して名前を与えられただけの仮の存在であることを理解することができるでしょう。チャンドラキールティは『入中論』の中で、馬車をたとえに用いて「自我」のありようを説明しています。馬車という概念を主題として、馬車の存在を分析してみると、馬車を構成しているそれぞれの部分とは無関係に、独立して存在している形而上学的で実体を持った馬車を決して見つけることはできません。しかしそれは、馬車が存在しないということではありません。これと同様に、「自我」や「自我の本質」を主題としてそのような分析をしてみると、各個人の構成要素であるからだと心とは全く無関係に、独立して存在している「自我」を見つけることはできないのです。このように、「自我」とは他のものに依存して存在しているものに過ぎないということを理解したならば、それを他の有情たちの存在についても適用して理解する必要があります。他の有情たちも同様に、からだと心という構成要素に依存して、単なる名前を与えられただけの仮に設けられた存在なのです。このように、私たちは肉体的・精神的な存在であり、有情が持つ精神的・物理学的構成要素である五蘊に依存して存在しています。