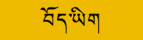インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ
今朝ツクラカンでは、今回の灌頂をリクエストしたパルプン・シェラブリン僧院とヒマーチャル・プラデーシュ州のチャンゴからの700人の僧侶、尼僧、在家信者を含む、56ヶ国から集まった8,500人の聴衆がダライ・ラマ法王を出迎えた。法王は相好を崩し、手を振りながら公邸の門から本堂までの道のりをしっかりした足取りで歩かれた。

法王は法座に着くと次のように告げられた。
「今日はタイシトゥ・リンポチェが私の横に同席されています。リンポチェが観音ジナサーガラの灌頂を私にリクエストされました。観音菩薩の行法は四部タントラ(所作・行・ヨーガ・無上ヨーガ)のどの部においても実践されていますが、観音ジナサーガラの行法は無上ヨーガタントラに属します」
法王は観音菩薩は慈悲を体現する至高の本尊であると述べ、観音菩薩を讃えるいくつかの偈頌を誦経された。
法王は次のように話を続けられた。
「今日は灌頂授与の前行修法(準備の儀式)を行いますが、ツォンカパ大師の『菩提道次第集義』の口頭伝授のリクエストも受けていますので、今からその法話を行います。その前にまず『般若心経』を唱えます」
タイシトゥ・リンポチェがマンダラと仏陀の身・口・意の象徴を捧げた後で、法王はタイシトゥ・リンポチェとは長年のよき友人関係にあり、リンポチェは揺るぎない忠誠心を私に示してくれていると述べられた。
法王は、ツォンカパ大師がアティーシャの『菩提道灯論』を基に『菩提道次第広論』『菩提道次第中篇』『菩提道次第集義』の3篇を著されたことに言及された。『菩提道次第集義』のテキストは、仏陀への礼拝文に続く文殊菩薩への礼拝文で始まっている。
「仏陀の教えは信心のみに依るものではなく、論理的な考え方に根ざしていますので、どの仏陀のお言葉も論理にかなっているかどうかを確かめることができます。後にナーガールジュナ(龍樹)のようなナーランダー僧院の導師たちは、仏陀の教えを論拠に照らして検証し、仏陀が比類なき師であることを立証することがいかに大切であるかを示されました」

「インドには、すべての精神的伝統に対して敬意を払うという、長年のよき慣習があり、この地で様々な伝統が栄えてきました」
「私は仏教の僧侶として仏教論理学や認識論を勉強し、唯識派が提唱する認識の主体と対象の二元性を否定する見解などが、論理に照らして検証され得ることを学んできました。今日では科学者でさえ、心と感情の働きについて仏教が提示する、広大で根拠に基づく説明に敬服しています。僧院に入った子どもたちは心と意識について学び、51の心所(心に伴って派生する心の働き)などについて勉強します。私自身について言うならば、般若学や中観の教えと共に、論理学概論、仏教心理学などについて勉強してきました。古典的なテキストを学ぶことはとても大切で、私もそのいくつかを暗記しました」
ここで法王は、ツォンカパ大師の『縁起讃』の一節を想起され、その内容をご自身の実践に重ね合わせて説明された。
法王は亡命してから、パンディット・ネルー氏が首相を務めるインド政府に支援を求めたときのことを思い起こされた。そして、最初にチベット人の子どもたちが自国語で学べる学校を創設することと、後にチベットにおいて学問の拠点であったいくつかの僧院を南インドに再建することを請願されたのである。
そして法王は7世紀のチベットに遡り、ソンツェン・ガンポ王が中国との深い結びつきにも関わらず、インドの文字であるデーヴァナーガリーのアルファベットを手本にチベット文字を作られたことを説明された。その一世紀後にシャーンタラクシタ(寂護)がチベットに招聘されたが、チベット文字の存在を知ったこの導師は、仏教典籍をチベット語に翻訳することを強く勧められた。そのお陰で完成したのが仏陀のお言葉であるカンギュルと、その註釈書のテンギュル、合わせて300巻あまりの翻訳書である。それから後も数々のチベット人の学者によって1万冊以上の註釈書が記されている。
中国共産主義者はチベットの仏教文化を取り締まろうとしているが、そのような試みが成功することはなく、チベット仏教哲学が中国共産主義よりも深遠であることは明らかである。共産主義イデオロギーとは対照的に、チベット人は仏教的な民主主義を僧院と尼僧院の中で実施している。チベットの伝統は広大で奥深く、深遠であり、現代科学と融合する可能性を秘めている。
法王は、今日は月曜日なので、今朝、内科医たちと会って脈診、尿診などを受けたが、皆そろって法王が完全に健康であることを請け合ったと漏らされた。そして法王は快活に笑いながら「ラモ・ドゥンドゥプ、キ・ヒヒー!」注と叫ばれた。
注:“ラモ・ドゥンドゥプ” は法王の幼名。“キ・ヒヒー” はチベットのカム地方などでよく使われる雄叫び。
法王は『菩提道次第集義』の偈頌を読み進めながら、深遠な系譜と広大な系譜という二つの修行道の伝統と、その創始者であるナーガールジュナおよびアサンガ(無着)に払われている敬意についてふれられ、両伝統の実践は、短期的・長期的な目標を実現するものであると述べられた。

次の偈頌は菩提道次第の四大徳性を概説している。
法王は、テキストに繰り返し出てくる “修行者である私も、このように修行した。解脱を求めるあなたもまた、同じように修行するべきである” というフレーズが最初に記された偈頌までくると、ツォンカパ大師は元々このように書かれたが、テキストが祈願文として唱えられるようになると “尊き我が師はこのように修行された。解脱を求める私もまた、同じように修行しよう” と言い換えられていることを明らかにされた。
そして、次の偈頌から中級者の修行道についての記述が始まる。
法王は、もし今もチベットに居たなら、世界に対する理解を深め、広げていくことはできなかったであろうと述べられ、実際に亡命先でさまざまな職業や社会的地位にある人々と出会い、彼らから学んできたこと、また、インターネットや携帯電話などの技術革新により、世界中の人々と意見交換ができるようになったことに言及された。
法王は、シッキム王国の元インド政務官アッパ・パント氏が、スワラグ・アシュラムに法王を訪ねたときに述べた言葉を紹介された。パント氏は遠景を見渡しながら「法王がここに滞在され、法王の言葉の光がここから世界中に広がっていくことは、とても素晴らしいことです」と言ったという。
また、アメリカの議会議員から「中国人民解放軍は100万人の兵士で構成されているが、たった一人のダライ・ラマを凌ぐことはできない」と指摘されたこともあると話された。

“布施〔の修行〕は、有情の願いを叶える如意宝珠のようなものである” で始まる偈頌からは、布施・持戒・忍辱・精進を経て禅定と智慧に至る六波羅蜜の説明に入る。
法王はチャンドラキールティ(月称)が『入中論』で説明している、“事物に客観的な固有の実体があるとするならば、それによって四つの論理的誤謬が生じる” という点について触れられ、ご自身が毎日の瞑想の中でこの四つの誤謬を熟考していることを明らかにされた。そして個人や意識、何であれ、何かについて考えるとき、そこには何らかの客観的で独立した実体があるように見えるものだと述べられた。否定する対象が心に現れ、それを論破しようとするとき、事物がどのように存在するのか、その真の分析を行うのである。
1)固有の存在(自相)があるかどうかを分析した後で、聖者の心は空と一体の禅定に入る。もし固有の存在があるならば、それは聖者の心によって見出されるはずである。もし固有の存在があるならば、聖者の空性における等引がそれを破壊することになるが、(それは論理に反する)。
2)もし他の要因に依存しない固有の存在があるならば、世俗の真理(世俗諦)は究極の分析に耐えられなければならないが、(それは論理に反する)。もし固有の存在を指し示すことができるなら、それは究極の分析に耐えられるはずである。しかし瑜伽行者はこれだ、あれだと言って指し示せるものを何も見出さない。他の学派では、正しい認識の対象は客観的に存在する何かであるはずだと言うが、正しい認識は、知覚された事象を対象に行われる認識である。
下のクラスの哲学学派は、自己定義された固有の存在をもつ正しい認識があるべきだと主張するが、もしそのようなものがあれば、その認識対象は究極の分析に耐え得ることになる。実際には固有の存在をもつ対象など存在せず、それはただ世俗において名付けられたものである。
もし事物にそれ自体の心髄があるならば、世俗の真理が究極の分析に耐え得るという論理的誤謬を犯すことになる。

3)もし事物の心髄が因によって生じるならば、究極の結果があることになり、4)現象の自性は空であるという仏陀の教説は真実でないことになる。何かが空であると言うとき、分析している対象それ自体の固有の存在が空であると言われているはずだ。
法王は『入中論』第6章の最後の数偈を誦経して考察をまとめられ、ご自身が見道に至ることを切望された。
そして法王は、チャンドラキールティが、“『入中論』で解説された真如は深遠で恐るべきものであり、以前よく修習していた人なら必ず理解するであろうが、それ以外の他の人々は、これを広大に聴聞していても理解できないだろう” と忠告されていることを付け加えられた。
次に法王は、明日授与する観音菩薩の灌頂の前行修法の準備に入られ、その間、灌頂を授かる弟子たちは “オーム・マニ・ぺーメ・フーム” の真言を詠唱した。法王は何度生まれ変わっても必ず観音菩薩に庇護されるように、受者がマンダラに入ることを鼓舞された。
前行修法の一環として発菩提心の儀式が行われ、加持された水、守護の紐、長短2種類のクシャ草が配られ、一人一人が今夜の夢に注意を払うように促された。
法王は今日の行事をすべて終えると、「明日またお会いしましょう」と告げられた。