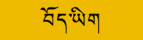インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ
今朝ダライ・ラマ法王は、とてもにこやかにネット中継が行われる居室に入り、スクリーンに映し出されたアジア各国の仏教徒たちの顔をご覧になると、彼らに手を振って挨拶をしてから席につかれた。シンガポールのパオ・クワン・フォー・タン寺院の尼僧たちが『般若心経』を中国語で唱え、続いてインドネシアの団体であるダルマヤトラの人々が同じく『般若心経』をインドネシア語で唱えた。

法王は、始めに『般若心経』の帰敬偈を静かに繰り返された。
続いて法王は次のように述べられた。
「今日は、アジアの仏教徒のみなさんがリクエストされた法話会の2日目です。皆さんは、仏法や般若波羅蜜の教えの目的は何なのかと疑問に思うこともあるでしょう。ひとつの答えが、漢族の方が『般若心経』の最後に唱える祈願文の中にあり、仏法の修行を要約しています」
「なぜ執着・怒り・無知という三毒を根絶しなければならないのかと言えば、究極的には智慧を育み、障害を克服して菩薩行に従事するためであり、利己的な目的ではなく、一切有情が悟りを得るための助けとなるためです。このよくまとめられた祈願文はとても感動的です。この祈願文が付された『般若心経』は仏法の心髄を示しています」
「私たちが苦しむのは自分の心をコントロールすることができないからです。十二支縁起は苦に至るプロセスを説いており、その第一は根源的無知(無明)です。仏陀の教えは根拠と論理に基づいており、苦しみと喜びはこの世の創造主がもたらすのでもなく、原因や条件なしに生じるのでもありません。インドには “アヒンサー(非暴力)”、すなわち誰をも害さないという長年の伝統があり、好戦性や攻撃性の対極となっています。こういった破壊的な感情は無明から生じ、無明はかき乱された心から生じるのです」
「私たちが持っている知性を活かせば活かすほど、苦しみの原因となる悪業を避け、幸福の原因となる行為が増していきます。無明はただ祈ることでは除くことができないし、洗い流すこともできません。他者や事物がそれ自体で独立して存在し、客観的に実在すると見てしまう無明をなくすには、もののありようの本質を分析しなければなりません」
「『入中論』第六章の最後の方にある偈に、このように書いてあります。

「私はこの三つの偈を何十年も熟考した結果、苦しみが断滅した境地に至ることは可能であると確信しました。すべての過失を滅し、修行道を歩んで悟りを得ることは可能であり、私たちが見道に至れる希望はあるのです」
「私たちには誰にも仏性が備わっています。私たちの心の本性は、明らかで、対象を知ることができるものであり、最も微細な心には光明と明知という倶生の本源的な徳性が備わっています。そのレベルでは煩悩も汚れもありません。心を汚す障碍は心の本質と一体ではなく別なので、無明などの煩悩は対策を講じることにより滅することができます。このことを理解し、世俗諦(世俗の真理)と勝義諦(究極の真理)の真のありように対する理解と結びつけることができたら、一切智の境地へと導かれることでしょう」
「このように述べているのは、経典に書いてあるからではなく、菩提心を育み、空性を理解することが心を変容するために効果があると私の経験が示しているからです。資糧道、加行道、見道、修道、無学道へと五つの道の階梯を進むことは可能であり、仏陀の境地に至ることは可能なのです。この境地を知ることが教えの真の味わいを得ることになるのであり、自らの心をよりよく変容しようと努力することが必要です」
「『入中論』のテキストは甚深・広大の両方の道を説いていますが、一方でナーガールジュナ(龍樹)の『根本中論偈』は智慧の道が主眼となっています」
ここで法王は『入中論自註』の昨日終わったページから再び読み始め、チベット語で悟りは「チャン・チュプ」という言葉であると解説された。「チャン」はすべての煩悩の浄化を意味し、煩悩が滅したなら、心に本質として備わる光明と明知によってすべてをありのままに見ることができるようになる。「チュプ」は一切法を完全に知ることを意味する。
また、人はそれ自体で独立して存在しているのではないと知るだけでは十分でなく、人には固有の実在性など微塵も存在しないのだと理解する必要がある。“私” という感覚は心と体の結合、つまり心と体の集合体に依存している。ナーガールジュナは『宝行王正論』で次のように述べられている。
チャンドラキールティも、事物はそれ自体に固有の相(特徴)を欠いていることを熟慮し、それなら事物はまったく存在しないのだろうか、と自らに問われた。そして、心と体の集まりである五蘊に対して、単に名前を与えられただけのものとして人は存在しているに過ぎない、との答えを出されたのである。

私たちには “私” という感覚があるが、その “私” を構成する五つの要素の集まり(五蘊)を見てみると、それらの要素には客観的で固有の実体は存在せず、全体としての “私” にもそれ自体の側から独立して存在する実体は存在しない、ということが分かる。
『入中論』のテキストでは、ここから十波羅密の解説に入る。最初は布施波羅密で、覚醒した境地に至る根本因となるものである。チャンドラキールティは次のように述べられている。
質疑応答において法王は、自分の体、言葉、心について考える時には、それらを所有する確かな “私” という感覚があると繰り返された。しかし、もしその “私” を探すならば、そのような “私” は見つからない。だからといって、自分がまったく存在しないということではない。『入中論』では、世俗において日々活動する “私” は、心と体の集まりに対して単なる名前を与えただけの “私” として、否定されるべきものではない。この “私” は独自の相(特徴)を持つものの如くに心に顕れるが、そのような独自の相は実体を持って存在しているのではないのである。
次に法王は、良い結果をもたらす行いが善いカルマ(行為・業)と呼ばれ、悪い結果を引き起こす行いが悪いカルマだと言われる、と説明された。後者の根本にあるのは無明と利己主義である。
困難に直面した時に不安や不幸を感じることは自然なことであるが、そのために無気力に陥るのは無益なことである。気候変動問題を考えてみても、憂鬱になるより、自信を持ち、植林するなどの前向きな行為を取るべきである。法王は、問題の原因は何であるのかをよく調べ、その原因が克服可能であるかどうかを判断するようにと勧められた。克服可能であるなら、その手段を実行すべきであり、克服不可能なものならば、それを心配しても解決にはならないのだから、心配する必要はない。
身近な人の死をどう考えるべきかという質問に、法王は次のように答えられた。
「私たちの体は両親から受け継いだものです。しかし、精子と卵子の結合だけで人間が生まれることはありません。第3の要素として、意識が必要です。意識の源は一瞬前の意識であり、意識の連続体が続いているから、何人もの子どもたちが前世を思い出すことができるのです。両親のように身近な人が自分と強い縁があるならば、将来また互いに出会うこともあるでしょう」

自分自身の死にどう備えるかについて、法王は執着と怒りを手放すことが重要であると答えられた。仏教徒であれば、仏像など仏陀を象徴するものを近くに置くこともあり、チベット人が法王の写真を携えているようなものである。重要なことは、死のプロセスにおいては自分が意識を集中しやすい徳のあるイメージを何か近くに持つことである。また可能であれば、菩提心を思い起こすことがとても役に立つ、と法王は付け加えられた。
法王は、朝目覚めたその瞬間から菩提心に考えを巡らせていると述べ、菩提心以上に悪業を浄化し、功徳を積むために効果的なものはないとも言われた。良い心の持ち主には友人がたやすく集まるように、菩提心を育むことは日常生活においても有益なのである。
独立した自我が存在するという強い思いを抱き続けていると、心の平安は乱されやすい。そのような思いは、空についての明確な理解を培うことで滅することができる。
ここで法王は、これから発菩提心の儀式を行うと告げ、一切ヨーガの発菩提心を通して、まず菩提心の短い瞑想を、次に空性の短い瞑想を参加者全員で行うよう導かれた。
最後に法王は、次のように締めくくられた。
「皆さんは菩提心の教えを受けられたのですから、これを毎日の修行として下さい。しばらく続ければ、何らかの変容が見られるでしょう。私は菩提心と空性の瞑想を数十年にわたって続けてきた結果、私の心によき変容を見出しています。私にできたのですから、あなた方にもできるのだと、心に刻んで下さい」
司会者が、教えを説かれた法王へ感謝の言葉を述べ、さらに開催実現のために尽力してきた関係者すべてにも感謝の意を表した。そして法王が普賢行願讃の廻向文を唱えられて、法話会が円満に終了した。