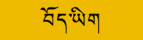インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ
今朝、ダライ・ラマ法王は、オンライン法話会の主催団体であるイタリア仏教徒連合(Italian Buddhist Union)に敬意を表して挨拶し、着座された。早速、イタリア語で『般若心経』が唱えられ、法話会が開始された。『般若心経』を唱え終わると、イタリア仏教徒連合のフィリッポ・シアナ会長が連合を代表して法王を歓迎した。この連合のメンバーは仏教のさまざまな伝統の宗派によって構成されており、メンバー達は仏教に関心があるのみならず、必要とされる場所で人道的な援助を行い、他の宗教の伝統とも友好的な関係を築いているのだと説明した。さらにシアナ会長は、法王がメンバーにとってのインスピレーションの源であり、法王に教えを説いてほしいとお願いした。

これを受けて、法王は次のように返答された。
「今日は、あなた方イタリア人の皆さんからのリクエストに応じて、四聖諦(四つの聖なる真理)と二諦(二つの真理)について解説したいと思います。世界には、多くの異なる宗教の伝統があります。それらの宗教は、哲学的な見解においてさまざまな違いがありますが、愛と思いやりの重要性という点においては共通のメッセージを発信しています。インドでは、過去三千年ほどの間に “アヒンサー(非暴力)” と “カルーナ(慈悲)” の実践が盛んになりました。さらにインドでは、世界の主要な宗教が平和に共存しています」
「東西の交流が深まるにしたがって、パーリ語とサンスクリット語の伝統に基づく仏教の教えに興味を持つ人が増えてきました」
「シャーンタラクシタ(寂護)がティソン・デツェン王によってチベットに招聘された時、シャーンタラクシタはナーランダー僧院の仏教の伝統を紹介しました。シャーンタラクシタは仏教哲学の偉大な師であるばかりでなく、論理学や認識論にも長けており、その著作である『真理綱要(Tattvasamgraha)』と『中観荘厳論(Madhyamakalalamkara)』によってもそのことが明らかに示されています」
「四聖諦は、仏陀の教えの根本的な土台となっています。しかし、悟りを開いた直後に釈尊はこのように述べられたと伝えられています」
「しかし、釈尊はかつての5人の修行仲間に出会った時、彼らから教えを説いてくださいと懇請されました。そこで釈尊が彼らに説いた教えが四聖諦でした」
「サンスクリット語の伝統によれば、釈尊は3回法輪を回し、3つの教えを説いたとされています。初転法輪で説いたのが四聖諦で、その本質・働き・結果を明らかにされました。釈尊がその本質について説いた際、苦しみについて知るべきである、苦しみの原因を滅するべきである、苦しみの止滅を実現するべきである、そのために修行道を実践するべきであると述べられました。さらに無我の見解に加え、滅すべき原因である悪しき行為や煩悩に関するより詳しい教えは第二法輪と第三法輪で説かれました」

「四聖諦の結果に関しては、釈尊は次のように述べられました。苦しみを完全に知ったので再び知る必要はない。苦しみの因を完全に捨てたので再び捨てる必要はない。苦しみの止滅に至ったので再び止滅に至る必要はない。苦しみの止滅に至る修行道を実践したので再び実践する必要はない。つまり、行為と煩悩をすべて克服したので克服するべきものは何もない、ということを示されたのです」
法王は、チベット人が理由と根拠を拠り所として釈尊の教えに従っているのは、シャーンタラクシタのおかげであると感謝の意を示された。また釈尊の教えの中でも、特に心の働きに関する部分は、科学者たちにも通じるものがあると指摘された。世界の平和は、個人がそれぞれの心の中に平和を育んでこそはじめて実現されるものだという理解が広まっているのもこれと関係している。
四聖諦を正確に理解するためには、二諦を理解する必要がある。これに関して法王は、チャンドラキールティ(月称)の『入中論』の偈を引用された。
この偈が示しているのは、他のものに依存せずそれ自体の力で独立して存在するような実体はどれだけ精査したとしても見出すことはできないが、世俗においては名前を与えられただけの名義上のものとして存在するということである。真実や事物の本質的な存在に関する無知による誤解は、空の理解によって滅せられる。あなた自身の中に滅諦(苦しみの止滅)が成就された時、この真実はあなた自身の経験によって実証されるだろう。

法王は、世俗諦(世俗の真理)と勝義諦(究極の真理)の「二つの真理」に光を当て、白鳥の王者が両翼を広げて彼岸に飛んでいく喩えに結びつけた『入中論』第6章の最後の偈を引用された。そして、これらの真理に耳を傾け、考え、瞑想修行を積んでその経験を自分自身の心に馴染ませるという聞・思・修の実践を聴衆に勧められた。
法王は、仏陀の教えを理由と根拠に照らし合わせて理解することの重要性を繰り返し述べられた。また、中観派の見解と論理学を比べ、それらを2頭一緒にくびきをかけられた獅子のことわざを例に挙げて説明された。この2つの伝統は、シャーンタラクシタや、チャパ・チューキ・センゲ(1109 - 1169)、サンプー僧院長などのチベット仏教の偉大な導師たちによって紹介され、後にチベットにおける問答の方式として確立されていったのである。
法王は、モニターに映し出された聴衆からの質問に答える際、ボン教の伝統に触れられた。ボン教は、ソンツェン・ガンポ王に嫁いだ中国の王女によってもたらされた仏陀釈迦牟尼のジョヲ像がラサに到着する前に存在していた伝統である。その後、シャーンタラクシタは仏教王ティソン・デツェンに、インドの仏教文献をチベット語に翻訳するよう勧めた。仏教は定着したが、ボン教の伝統は今もなお残っている。
最近、欧米では仏教に興味を持つ人が増えているが、ユダヤ教やキリスト教の伝統は尊重され続けるべきである。法王は、すべての宗教が倫理と思いやりの重要性を教えていることを改めて強調された。

法王は、釈尊が苦行生活を修行に取り入れ、釈尊の多くの信奉者も同じように苦行を行ったと見ておられる。彼らの修行の基礎となっているのは戒律(ヴィナヤ)である。しかし、誓いを守ることができればそれに越したことはないが、心温かい人になるために、必ずしも誓いを守るという必要はないと法王は述べられた。
法王は、50年後の仏教の未来がどうなるかについての質問で、それに答えるのは難しいと述べられた。前仏陀の迦葉仏(カーシャパ)の時代は終わりを告げたが、仏陀釈迦牟尼の教えは今もなお広まり続けている。しかし、地球温暖化がもたらす脅威は、単に水の供給ができるかどうかだけにとどまらず、未来がどうなるかの保証も持てないことを意味する。
次に、破壊的な感情(煩悩)が生じた場合について質問された法王は、執着や嫌悪感を抱くのは、私たちの側から見れば、事物が堅固な実体を持つものとして存在しているかのように現れるからだ。しかし実際は、他の原因や条件に依存して事物は生じており、現れどおりには存在していないことを理解できれば、執着や嫌悪に対する反応のしかたも変わってくるであろうと説明された。
量子物理学の世界でも事物は現れているようには存在していないとされるが、それも外界の存在に対する挑戦のように見えるかもしれない。このことは、外界における客観的対象物とそれを見ている主体者の意識は同じ本質を持っているという唯識派との論争を彷彿させる。このような考え方は精神的な苦痛を和らげるかもしれないが、無知を根絶するためには、事物は単に名前を与えられたことによって存在しているに過ぎず、それ自体の側から独立して存在しているものは何もないという中観帰謬論証派の見解を理解する必要がある。
苦しみは悟りへの道として転換させていくことができ、特に菩提心の修行においては、苦しみによって悪業が浄化されることを願うことができると法王は助言された。そして、次の上師供養(グル・ヨーガ)の偈を引用された。
法王は、菩提心の他の側面である謙虚さは、自分を他者より劣っていると見なすことだと表現されうるが、それは落胆することではないと強調された。菩提心は広大な宇宙の生きとし生けるものを悟りへと導く願いに繋がるものであり、大きな勇気が必要である。他者を大切にする実践が強まることで、このような勇気が生じ、それが大いなる慈悲を高めることになる。大いなる慈悲の心があれば、他者が苦しみを克服することを助ける不屈の精神を持つこととなるであろう。

阿羅漢の涅槃と仏陀の法身との比較について問われた法王は、阿羅漢は煩悩という障りを克服したけれど、煩悩の習気(習慣性の力)である微細なレベルにおける障り(所知障)が残っているのに対し、仏陀はそれら全てを滅した存在であるとお答えになった。
空性の理解を助けるために推薦する偈頌は何かと尋ねられた法王は、ナーガルジュナ(龍樹)の『根本中論偈』の一つの偈を挙げられた。
法王はまた、チャンドラキールティの『入中論』第6章からいくつかの偈も述べられた。
法王ご自身は繰り返しこれらの偈を唱えており、すべての現象は分析によってその実体を見出すことはできないが、世俗のレベルにおいては単に名前を与えられただけものとして存在するのである、という偈が示すことを熟考されている。
ジョバンナ・ジョルジェッティ氏は、短い感謝の言葉の中で、法王のご長寿を願い、再びイタリアを実際に訪問してくださることを望んでいると述べた。
ここで法王は、発菩提心を養うための菩薩戒授与の儀式を執り行う意向を示された。そして、仏陀や菩薩などのお姿をありありと観想し、基本的な3つの偈を法王の後に従って3回復唱するよう受者たちを導かれた。
最後に法王は、『インド古典仏教における心の科学と仏教哲学』第1巻「物質的世界」のイタリア語訳が刊行されたことに関して、翻訳者に感謝の意を表した。