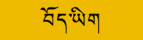インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ
ダライ・ラマ法王は、朝の暖かく湿った空気の中を、法王公邸から徒歩でツクラカンに向かわれた。本堂とその周囲は、約8,000人の一般聴衆、TCV(Tibetan Children’s Village:チベット子ども村学校)の9〜12年生の生徒400人、チベット人の大学生800人で埋め尽くされていた。

法王は、チベット人の若者に向けたこの法話会は2007年に法王ご自身のお考えによって始められたもので、若いチベット人たちに仏教の教えを説くことを目的としており、今回のテキストは、ギャルセ・トクメ・サンポの『三十七の菩薩の実践』である、と述べられた。
「ここに集まった学生の皆さんはインドで生まれたかもしれませんが、あなた方の祖先はチベット人です。チベット人である私たちは、死ぬまでチベット人であり続けます。チベット人の起源についての神話には、私はあまり関心がありません。しかし、チベットの地には、3~4万年前から人々が住み続けてきたという考古学的な証拠があります。いずれにしても、私たちチベット人の特殊な点は、チベットの宗教と文化にあります。7世紀の仏教王ソンツェン・ガンポは、チベット語で経典を記すための文字を作成するように命じました。これを受けて、インドのアルファベットに基づいて母音と子音から成るチベット文字が作られました。チベット語の話し言葉は、中国の言語ともインドの言語とも異なりますが、チベットの文字はインドの言語であるサンスクリット語をモデルとしています。

「8世紀になると、仏教王ティソン・デツェンの招聘を受けて、シャーンタラクシタ(寂護)がチベットを訪れました。彼は、チベットには独自の言語があるのだから、サンスクリット語に頼らず、チベット語で仏教を学ぶべきだとアドバイスをされました。言い伝えによれば、彼は高齢であったにもかかわらず、チベット語を少し学ばれたそうです。また彼は、インドの経典や論書を可能な限りチベット語に翻訳するよう勧めました。その結果、仏陀のお言葉を記したカンギュル(経典)が100巻余り、後代にインドで記されたテンギュル(論書)約220巻がチベット語に翻訳されました。これらの経典や論書の冒頭には、そのテキストが正当な源を持つことを示すために、“〔本書のタイトルは、インドの言語である〕サンスクリット語では…、チベット語では…” と記されています」
「仏教は、昇る太陽のごとく、アジアの多くの人々に光をもたらしました。西洋ではキリスト教が広く浸透し、中東ではイスラム教が浸透しました。一方、インドでは、ヒンドゥー教の様々な宗派、ジャイナ教、仏教が栄えました。インドの大きな特徴は、世界の主だった宗教の信者たちが肩を並べて共存していることです。その雰囲気をよく示す一例として、パーシー教徒の共同体があります。彼らはゾロアスター教を信仰するペルシャに起源を持つ人々で、現在は少数しかいませんが、ムンバイで数百万人のヒンドゥー教徒やムスリム教徒に囲まれながら、何の不安もなく暮らしています。インドの伝統的な宗教は、お互いを尊重しあっているのです」

さらに法王は、仏陀が初転法輪で説かれた「聖なる四つの真理(四聖諦)」の教え、粗いレベルの無我、一点集中の瞑想(止)などは、最初にパーリ語で記されたことを述べられた。そして、第二法輪で説かれた内容は般若波羅蜜(智慧の完成)の教えであり、霊鷲山(ラージギール)の山頂で、清らかなカルマを持つ知性の優れた者だけを対象として説かれた。般若波羅蜜について説かれた多くの般若経典群は、その長さによって大・中・小に分類され、そのそれぞれがまた大・中・小に分類されている。広大に解説された『大般若経』が全12巻、中の大とされる『二万五千頌般若』が全3巻、中の中とされる『八千頌般若』が1巻あり、さらに短いテキストが小のカテゴリーの中にもいくつかある。

『般若心経』の中で述べられている「色即是空、空即是色」とは、すべての現象にはそれ自体の側から成立している固有の実体はない、という空の見解が説かれている。これは、何もないという意味ではなく、物質的存在(色)は、実際に目で見ることはできるが、その実体がどこにあるかを追求していくと、これがその物質の実体であると指をさして示すことのできるものはどこにも見つけ出すことができない、という意味である。事物は、究極的には私たちの目に見えているようなあり方では存在していない。量子力学に携わる科学者たちも、対象物自体の側から客観的に独立して存在するものは何もない、として、同じような見解を述べている。というのも、物質的存在は、因や条件などの様々な要素に依存して生じているため、他のものに依存せず、それ自体の側から独立して成立している固有の実体など、そもそも存在しないのである。
法王はさらに、第三法輪についても言及された。ヴァイシャーリーやその他の地域で、仏陀が『解深密経』にまとめられている内容を説かれたのが第三法輪である。第二法輪で一連の般若波羅蜜の教えが説かれた際に、対象物の空、つまり客観的な光明について説かれていたが、第三法輪では、対象物を見ている主体者の意識である光明の心、すなわち最も微細なレベルの意識について詳しい解説がなされたのである。そして法王は、次のように述べられた。
「瞑想をする時は、五感を通して生じる知覚能力ではなく、第六の純粋な精神的意識作用を使います。西洋では、純粋な精神的意識作用についてはあまり議論されることがなく、感覚的な意識についてのみ、脳の機能との関連で語られることが多いようです。しかし、脳だけを基盤として心や意識を説明することはできません。これに対し、古代インドには、心と感情の働きに関するすぐれた理解がありました。微細なレベルの心、ならびに微細な心が持つ光り輝く光明の心についての知識や、破壊的な感情は粗いレベルの心から生じることなどが認識されていました」

「チベットの伝統では、根本経典を暗記し、語句一つ一つの意味内容を学び、理解した内容について互いに問答する、という勉強法で学びます。論理学と認識論に関しては、ディグナーガ(陳那)とダルマキールティ(法称)の広範な著作がチベット語に翻訳されています。後に、サンプー僧院の僧院長であったチャパ・チューキ・センゲ (1109-69)や、サキャ・パンディッタなどの学者たちも論理学についての詳しい解説書を書いています。論理学と正しい根拠の拠り処(量)はとても役立つものであり、他に類を見ない素晴らしいものです。そのことを、若いチベット人の皆さんにぜひ知っていただきたいと思います。それは、私たちの誇りでもあるのです」

次に、法王は、『三十七の菩薩の実践』のテキストを読み始められた。このテキストは、「〔慈悲の顕現である〕ローケーシュヴァラーヤ(世自在観音)に帰依いたします」という帰敬偈から始まっていることを述べられたあと、1行目で述べられている「一切の現象は、来ることも、去ることもないとご覧になりながら、」とは、事物は私たちの目に現れてくるようなあり方では存在していないということが述べられている、と話された。法王は、チベット語の仏陀を意味する「サン・ゲ」という言葉の意味を解説されて、「サン」とは、すべての過失を滅したという意味であり、「ゲ」とはすべての良き資質を増大させた結果として、一切の現象をあるがままに見ることができるという意味であることを説明された。さらに、ツォンカパ大師は「実在論、あるいは虚無論という極端論(二辺)に陥ってはいけない」と述べられていること、煩悩には正しい根拠がなく、誇大妄想から生じるが、怒りの対治である慈悲や忍耐には正しい根拠があるということについて語られた。
さらに、テキストの第2偈以降では次のようなアドバイスがされている。 悪い影響を与えるような故郷を捨てるべきである、静謐な場所に依存するべきである、悪い友を捨てるべきである、それによって良い資質が育まれる。三宝(仏陀・仏法・僧伽)に帰依するべきであり、中でも、仏法こそが主な帰依の対象となる。なぜなら、仏法によって真の解脱と解脱への道が実現するからである。仏陀は教師であり、僧伽(聖なる出家者の集まり)という仲間に支えられて仏陀の教えを実践するべきである。仏陀は、私たちのなした悪業を水で洗い流すことも、苦しみをその手で取り除くこともできない。まして、仏陀ご自身が得られた悟りを私たちにその手で与えてくださることもできない。仏陀は、真如という真理を示すことで有情を救済されているのである。

第8偈では、罪ある行いを決してなさないように、と忠告されている。アーリヤデーヴァ(聖提婆)も『四百論』の中で次のように述べられている。
解脱とは、煩悩からの開放である。
次に、第10偈では、一切有情に思いを馳せ、彼らを利益するために仏陀の境地に至りたいと願う利他心を起こすべきことが菩薩の実践として説かれており、第11偈では次のように述べられている。
これを修行する方法は、ナーガールジュナ(龍樹)の『宝行王性論』やシャーンティデーヴァ(寂天)の『入菩薩行論』の中に詳しく述べられている。これに関連した偈頌が続いたあと、第18偈の後半には次のように述べられている。

事物は、それが現れているようなあり方では存在していない。テキストの第23偈には次のように述べられている。
量子力学では、観察者がいるから観察対象が存在する、と述べている。唯識派の見解では、「外界の事物には実体がない」と主張している点で中観派と同様であるが、一方で、「内なる意識には実体がある」と主張しており、中観派は、「いかなるものにも、それ自体の側から存在する客観的な実体はない」という見解を主張している。
さらに、テキストでは、「執着などの煩悩が生じるやいなや、すぐさま滅するべきこと」(第35偈)、「要約すると、いつどんな行いをしていても自分の心がどんな状態か、常に憶念と正知を維持して利他行を達成するべきこと」(第36偈)、「このように精進して成し遂げたすべての善行を悟りのために廻向すること、それが菩薩の実践である」(第37偈)と続いて本論が締めくくられている。
最後に法王は、仏教は「世俗の真理(世俗諦)」と「究極の真理(勝義諦)」という「二つの真理(二諦)」に基づいて説かれるべきことを奨励され、そうすれば、四聖諦をよりいっそう明らかに説明することができると述べられた。

法王は、さらに加えて、「すでにお話ししたことですが、ナーランダー僧院の伝統は、太陽のように光り輝く素晴らしいものです。今、亡命の地で自由を享受して生きている私たちは、この広大な生きた仏教の伝統を継承し、伝えていくことのできる機会に恵まれています。どうか、皆さんもそのために最善を尽くしてください」
法王はツクラカン本堂を後にされると、ゆっくりと回廊を歩まれ、何度も足を止めて、待ち受ける若者や高齢者の一人ひとりと挨拶を交わされた。人びとは、合掌して法王への尊敬を表しながら、法王と目が合うことを願うかのように微笑みを浮かべていた。そして法王は、階段の下で迎えの車に乗られ、短い距離を公邸に戻って行かれた。