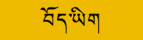インド、ビハール州ブッダガヤ
今朝のブッダガヤの濃い霧と冷たい空気も、ダライ・ラマ法王の教えを聴こうとカーラチャクラ・グラウンドに集まった5万人以上の聴衆の熱気を冷ますことはできなかった。ダライ・ラマ法王は、車で数分のところにあるチベット寺院から会場の巨大なテントの端まで移動されたが、聴衆に勝るとも劣らない快活なムードで彼らの熱気に応えられた。法王はステージの前面に昇られながら、会場の人々に向かって微笑みかけ、手を伸ばしたり、手を振ったりされた。

最初に法王は、ガンデン僧院の座主、前座主、副座主、サキャ・コンマ・ティジン・リンポチェ、リン・リンポチェ、各僧院長と副僧院長、転生活仏など、法王の法座の周囲に並んだ高僧方に挨拶をされた。
そして法王は次のように述べられた。
「今日の法話会の主催者は主にインド人グループですので、まずパーリ語とサンスクリット語でお経を唱えていただきます」
最初にパーリ語で『吉祥経』を含む一連の祈願文と礼讃偈が主催者グループの大人たちによって誦経され、続いてサンスクリット語の『般若心経』がインド人の学生たちによって唱えられた。

誦経の後に法王はお話を始められた。
「釈尊は成道された後、『深く(甚深)、静かで(寂静)、妄分別なく(戯論を離れ)、光り輝く(光明)、作られたものではない(無為)甘露のごとき法を私は得た。しかし、この法は誰に説いても理解できないだろう。それゆえ、私はこの森の中で、沈黙のままでいよう』と言われましたが、そう言われた理由の一つには、既存のインド哲学の伝統では、独立して自ら存在する自我が在り、その連続体が途切れることなく前世、今世、来世へと輪廻すると主張されていたことが挙げられます。釈尊は独立自存の自我が存在するという観念への執着こそが精神的な苦悩をもたらす源であると見抜かれ、無我を悟られましたが、無我の概念を理解する人はほとんどいないだろうとお考えになったのです」
「しかし、結局サールナートで教えを説かれるに至り、その後、霊鷲山の王舎城(ラジギール)において、実体ある存在は何もないことを説き明かされました。初転法輪の教えでは、苦しみが存在するという真理(苦諦)と苦しみには原因が存在するという真理(集諦)を、第二法輪では空性についての教えを詳しく説かれましたが、『解深密経』には第三法輪で依他起性(他のものに依存して生起する現象)、遍計所執性(妄想された分別としてのみ存在する現象)、円成実性(完全なものとして達成された現象)について説かれたことが記されています。依他起性には遍計所執性が存在しないことから、空性である円成実性が示唆されます。また、第三法輪の教えで釈尊は、如来蔵思想と共に無上瑜伽タントラの修行の土台である光明の心について触れられました」
「マハーカーシャパ(大迦葉)とその弟子たちは戒律(律)と論蔵(論)の教えを保持し、それはパーリ語の伝統の礎になりました。その後、仏法への理解が深まるにつれて、ナーガールジュナ(龍樹)と他の弟子たちが、論理に照らして教えを分析し、それがナーランダー僧院のサンスクリット語の伝統になりました。釈尊の教えは興隆と衰退に直面しながらも、経典と論理を典拠として今も存続しています」

法王は、釈尊が弟子たちの気質、関心、能力に応じて様々な教えを説かれたことについて論じられた。釈尊は五蘊について、ある時は、それが自分とは別個の、自分が担ぐ荷物のように実体があるものだと説かれたが、別の弟子たちに対しては、外界に実体を持って存在するように見える物事は、それを捉えている主体者の意識と別個の実体ではない、と説明された。また、何ものにもよらず、自ら存在するものなど何もない、と説かれたこともあった。これを『般若心経』では、「色即是空、空即是色」と述べられている。
法王は、仏教は中国やチベットではなくインドで発祥したこと、ナーガールジュナなどのナーランダー僧院の導師たちもインド人であったことを強調された。そして今日の教えの主な弟子たちがインド人であることを幸運なことであると述べられた。二千年以上にわたって仏教はアジア全域に広まったが、チベットで保たれてきたナーランダー僧院の伝統が今日インドで再興されれば、申し分ないことであると話された。

仏教では非暴力の精神に基づいた行いが重要である。また物事を苦しみ、痛み、喜び等として捉えるのは自分自身の心なので、それらをどう感じるか、その決定権は自分にあるとも説かれた。他者を助け、幸せにする行動は善なるものであり、他者を傷つける行いは不善なものであるとみなされる。
法王はインドにおける世俗の倫理について触れられ、次のように話された。
「インドでは、長期にわたって様々な宗教の伝統が調和を保ち、共存してきました。この国では全ての信仰を平等に尊重するという世俗の倫理が行きわたっています。それを保ち続けなくてはいけません。一方で私は、この国に古代インドの智慧を復活させることに最善を尽くしています。しかし結局、最も大切なことは私たちがひとりの善い人間になることです」

「今を生きる70億の人口のなかで、1億の人々は宗教的実践に興味がありません。しかし興味がある人のなかに、宗教を差別の土台にしてしまっている人々がいます。宗教が争いの元凶になるとは本当に悲しむべきことです」
「人間は社会的な動物であり、お互いがお互いを必要としています。一人で生きていかれる人などいないのです。ここでは皆が平和を享受していますが、他の場所に行けば紛争がたくさん起こっています。私たちは皆同じように幸せを望み、苦しみを避けたいと思っているのですから、釈尊の弟子として、どうしたら他者を助けることができるのか、毎日、自問自答しなければなりません」
「現代の教育システムでは、人間性について教える機会が殆どありません。やさしさと思いやりについて話し合う場を増やす必要があります。例えば、愛と思いやりのある家庭に恵まれれば幸せですが、嫉妬と競争心に翻弄されている家庭では幸福感は感じられない、ということは誰でも理解できるでしょう」

法王は、今回説かれる『転法輪経』と『稲芋経』に主題を移され、この2つの経典はどの仏教の教えにも共通する内容であることを告げられた。法とは心を変容させるもの、あるいは再構築するもの、という意味を内包すると述べられ、それについて七仏通誡偈を挙げて明らかにされた。
私たちの行いが、悪いものになるか善いものになるかは動機次第なのである。
法王は、釈尊の教えは経典の教えと、実践に基づく教えの二つに分類されることにふれられた。経典の教誡は口頭伝授と解説の伝授によって受け継がれてきたが、実践に基づく教えは戒律、禅定、智慧の三学を修めることに関連している。

『転法輪経』のなかで釈尊は、最初に苦しみについて理解すること、次に苦しみを滅することについて説かれている。これに関して法王は、ナーガールジュナの『中論』第18章5偈を引用された。
法王は、物事に実体があると捉える妄分別により苦しみが生じるが、この苦しみは灯明を捧げたり、儀式を執り行ったりすることで克服できるものではなく、縁起について分析し、考えることで取り除くことができると説明された。そしてナーガールジュナは、誤った見解を打ち破る方法を説かれた釈尊を賛辞し、ツォンカパ大師は縁起を説かれた釈尊に対して礼拝していることを話された。

法王は『稲芋経』を読み始められ、テキストにまつわるエピソードを語られた。この経典は、巨大で平らな岩の上で、シャーリプトラ(舎利子)とマイトレーヤ(弥勒)によって交わされた会話の内容である。お二人が岩に並んで座っていらっしゃったことは、地に足がついているという現実的な徳性を表わしている、と法王は賞賛された。二つ目のエピソードは、韓国の僧院長ウェン・ツェク師が著した般若経についての注釈書によれば、兜率天にいらっしゃり縁起を説かれた弥勒菩薩と同様に、人として誕生された弥勒の母君もまた弥勒と呼ばれたことが示唆されている、というものである。
法王の法話会は明日も引き続き行われる。