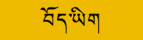インド、カルナータカ州 ムンゴット
シンポジウム3日目の第5セッションでは、神経科学、こころとは何かについて、そして、からだ、脳、主観的な体験とこころとの関係がテーマとなった。クリストフ・コッホ教授は発表の始めに、近代哲学の父とされるフランス人哲学者デカルトの命題「我思う、故に我あり」を引用した。「我思う」とは、意識の作用でありながら、科学の分野で意識についての関心が高まったのはつい30〜40年前であることを述べた。

何かを見る、聞く、覚える、空腹を感じる、といった感覚はどこかに存在するものだと思って、そのような感覚に捉われているのは唯一人間だけである、と一般的に考えられてきた。意識が生じるメカニズムについて、神経科学の分野では、大脳皮質の一部が欠けると意識は生まれないということが発見されている。犬や蜂など、小さくても高密度で複雑な脳を持つ動物や、胎児にも同様のことが当てはまるかは、現在のところ明らかになっていない。
ロドゥー・サンポ氏は発表のはじめに、意識については多くの問題がある、と話を切り出した。仏教では、意識と物質は別の属性を持つものと見なしており、意識は一瞬前の意識の連続体として捉えられている。心には、“光り輝き、明らかでものを知ることができる”という本質があり、それは5つの感覚器官を通して生じる感覚的な意識と純粋な意識作用の2つに分けられる。
発表後のパネルディスカッションで、法王はクリストフ・コッホ教授に、「誤った認識が疑いや智慧に変わることがあるかどうかを調べることはできますか」と質問した。コッホ教授は、「そのような実験にはたいてい実験用マウスを用いるので、それを実証する実験は、方法もなければ実行もできません」と答えた。クリス・インピー博士はマウスの代わりに役者を使ってはどうかと提案し、法王も、人間と実験用マウスとでは認識の性質に決定的な違いがあることを指摘された。

ゲシェ・ロブサン・テンジン・ネギ師は、仏教科学では心は物質的な存在ではないとしているものの、密教では意識とエネルギーはつながっており、微細なエネルギーに微細な意識が宿るとされている点を述べた。それに対し、コッホ教授は、「私の研究は人間の脳を外的な視点から分析することであり、脳の存在なしに意識の働きはないという立場を取っているのです」と繰り返し述べた。そこで議論が行き詰まったため、ミシェル・ビットボル教授は話をつなぐために、意識を育むという意識の側からの働きかけより、むしろ脳が意識の働きを広げる作用をしていると言えるのではないか、という質問を投げかけた。
午後の最終セッションでは、チベット文献図書館館長のゲシェ・ラクドール師によって、世俗の倫理観、つまり、人間の心に備わっている普遍的な価値を促進するための教育が必要とされていることについてのディスカッションが始められた。キンバリー・ショナー - ライクル教授は、子どもたちが思いやりを育むことにより、幸せや健康を促進するためのプログラムである「社会性と情動の学習」(Social and Emotional Learning)というこころの教育を実施しており、 その成果を発表した。その発表の中で、ショナー・ライクル教授は、学校教育を通して自己管理、自己認識、他者との共感、慈悲、利他的な態度、道徳的な判断について子どもが幅広い知識や態度、スキルを育むための取り組みについて説明した。

子どもが成長する過程で、世俗の倫理観を培う教育が必要な年齢、またその効果が最も効果的にあらわれる年齢について問われたショナー・ライクル教授は、「5〜7歳、10〜13歳、そして青年期が重要な時期ですが、それよりも大切なのは、子どもが学校に行き始めたその時から、全教育課程を終えるまで継続して学べるカリキュラムをつくることです」と答えた。
法王は、次のように述べられてシンポジウムを締めくくられた。「このような会議では、知識を深めるという目的はもちろんのこと、この世界に生きる70億の人間の幸せを考えることが重要です。20世紀に犯した間違いを繰り返さず、よりよい21世紀を築くには、若い世代がそれに必要な行動を起こす必要があります。私は仏陀の教えに従う一僧侶であると同時に、一人の人間であり、その努力を続けている人間です。どうか皆さんも私と同じように努力をしていただきたいと思います」